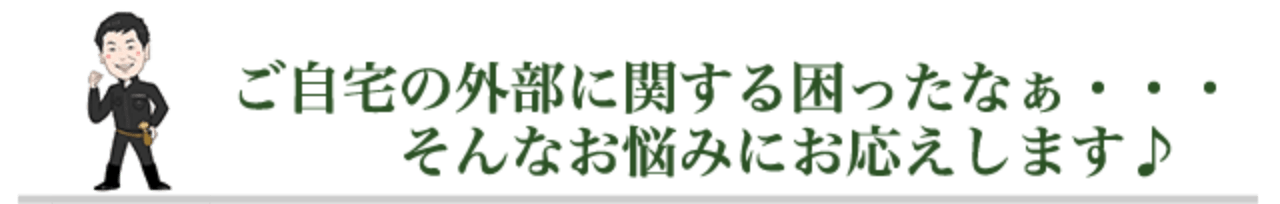北海道のアパートにおける「鉄部の劣化」は、
本記事では、北海道特有の気候条件が鉄部に与える影響や、
なぜ北海道の鉄部は傷みやすいのか?
1. 雪と融雪水による「長期の湿潤状態」
北海道では、11月〜
融雪水は塩分や凍結防止剤(塩カル)を含むことも多く、腐食(
2. 凍結と融解による膨張・収縮
気温が0℃付近を行き来する北海道特有の気候は、「凍結→融解→
この膨張収縮により、鉄部や溶接部、
3. 紫外線と寒暖差
冬場の低温、春秋の寒暖差、そして夏の直射日光によって、
北海道は冬の日照時間が短いため、濡れた鉄部が乾きにくく、
放置すると危険な鉄部劣化のサイン7選
1. 表面の赤サビ・黒サビが目立つ
最もわかりやすいサインが「赤サビ」。表面の塗装が剥がれ、
赤サビが黒サビや厚みを増すと、鉄自体が脆くなり、
2. 手すりのグラつき・動揺
鉄製の手すりを軽く揺らしてみてグラつくようなら、
特に2階以上の廊下手すりでは、
3. 階段の踏板に穴やゆがみ
アパートの鉄製階段は、踏板や桁、
特に冬場、踏板裏が雪や水にさらされやすく、
4. 塗装の剥がれと白サビ
鉄部の塗装が浮き、剥がれている箇所に「白い粉(白サビ)」
このまま放置すると、数年で穴あき・破断の恐れがあります。
5. 踊り場や外廊下にわずかなたわみ
鉄骨製の踊り場や外廊下がわずかに沈んでいる・
鉄部の「柱脚」や「接合部」が腐食により変形・
6. 雨水や融雪水の水たまり・排水不良
北海道では、
鉄部の下部が常に水に触れることで、見えない箇所(
7. 階段を上ると「ギシギシ」「バキッ」と異音
使用時に鉄製階段から異音がする場合、
見た目が無傷でも、
鉄部補修のタイミング|北海道だからこそ「夏前」が理想
北海道の補修タイミングは、6月~10月前半がベストです。
なぜなら:
- 気温が10℃以上で安定し、塗装や溶接がしっかり密着する
- 雪がなく、劣化箇所を正確に確認しやすい
- 冬に備えた安全対策として、秋までに施工が完了できる
冬場は凍結や積雪のため補修が難しく、
鉄部劣化を放置した場合のリスクとは?
- 入居者の転倒・転落事故→賠償リスク
- 倒壊・階段崩落による避難経路の喪失
- 建築基準法違反として是正勧告対象
- 物件評価の大幅な下落・退去率の上昇
- 修繕費用の高騰(補修では済まず、全交換)
特に札幌市内や近郊の物件では、「見えない鉄部の腐食」
地域密着の専門業者に相談するメリット
北海道に根ざした補修業者は、次のような点で優れています。
- 地域気候に応じた防錆ノウハウ
- 冬場でも状況確認・応急処置の体制
- 不要な全交換を避ける補修提案
- 共用部の補修に関する近隣配慮や段取りも熟知
特に、
まとめ|小さなサインに気づけるかが事故を防ぐ第一歩
北海道のアパート鉄部は、気温・湿気・積雪・
以下のようなサインが出ていたら、早急にご相談ください:
- サビが目立つ
- 階段がたわむ
- 手すりがぐらつく
- 異音がする
- 塗装が剥がれてきた
入居者の安全を守り、資産価値の維持・
北海道のアパート鉄部補修|
前回ご紹介したように、
そこで本記事では、具体的な解決策・修繕方法・補修の流れ・
1. まずは「現状把握」がすべてのスタート
 目視+打診+裏側確認が基本
目視+打診+裏側確認が基本
危険な鉄部の補修は、
- 目視点検:サビ・塗装の剥がれ・変色・たわみ・穴
- 打診検査:鉄部を叩いて音で内部の空洞や腐食進行を確認
- 裏面確認:踏板や手すりの裏側や接合部は劣化が最も進みやすく、
最重要ポイントです
とくに北海道では、融雪水や氷による裏側からの腐食が多く、
2. 鉄部補修には「段階別の対処」が大切
劣化状況に応じて、最適な補修方法は異なります。
【軽度劣化:塗装の剥がれ・表面の赤サビ】
 補修方法:
補修方法:
- ケレン(旧塗膜やサビの除去)
- 下地処理(錆転換剤や防錆プライマー塗布)
- 仕上げ塗装(ウレタン or フッ素系塗料)
 北海道ならではの注意点:
北海道ならではの注意点:
- 気温5℃未満の施工はNG
- 乾燥時間を十分に取る必要あり
- 表面が乾いていても、内部に湿気が残っていると再腐食の原因に
【中度劣化:鉄部の膨れ・穴・ガタつき】
 補修方法:
補修方法:
- 腐食部を切除または削り落とし
- 新規鉄板の溶接補強
- 手すりや踏板の取り替え溶接 or ボルト補修
- 表面の再塗装処理
 北海道の施工でのポイント:
北海道の施工でのポイント:
- 踏板や手すりを一時的に仮撤去・仮設し、
安全を確保しながら作業する - 外気の影響を避けるため、
ブルーシート仮囲いやストーブ加温など工夫が必要
【重度劣化:構造部材の変形・沈下・複数箇所の破断】
 補修方法:
補修方法:
- 階段全体や踊り場の柱脚補強
- 支持梁の入れ替え or ジャッキアップによる再固定
- 構造設計者の補強設計が必要になるケースもあり
 北海道ならではのリスク:
北海道ならではのリスク:
- 雪の重みで鉄部の傾きが増す前に補強を完了させること
- 1月~3月は作業が困難なため、秋までに実施が理想
3. 見落としがちな「排水・通気」の改善もセットで
鉄部の補修とあわせて重要なのが、「水を溜めない構造への改善」
 改善策例:
改善策例:
- 階段や踊り場の勾配調整
- 排水口の詰まり改善・新設
- 踊り場下部に通気スリットや換気穴を設ける
- 排水誘導プレートを設置して雨水を逃がす
北海道では凍結により水が滞留しやすいため、
4. 北海道で鉄部補修を成功させる業者選びの5つのポイント
- 鉄骨構造に強い専門業者であること
→ 塗装だけでなく、「溶接・構造補強・排水設計」
まで一括施工できる業者を選ぶことが重要です。 - 北海道の気候・凍結環境を熟知しているか
→ 凍結による膨張・融解などの影響を理解し、
適切な施工時期と施工方法を知る業者でなければ長持ちしません。 - 応急処置と計画補修の両面に対応できるか
→ 冬場に腐食が進行してしまった場合でも、一時的な仮補修を行い、
春に本補修できる体制があると安心です。 - 施工写真や工程管理を丁寧に行うか
→ 工事前・中・後の写真報告や図面提示がある業者は信頼できます。
- 強引な全交換を勧めず、補修提案が柔軟
→ 本来は補修で済むものを「全部交換しないと危険です」
と迫る業者には要注意。 コストとリスクを比較したうえで提案できる業者を選びましょう。
5. サークルフェローならではの補修スタンス
北海道の鉄部補修を数多く手掛けてきたサークルフェロー合同会社
 鉄部の腐食進行度を診断し、
鉄部の腐食進行度を診断し、段階別に最小限で最大の効果を出す補修  溶接・補強・防水・排水処理を一括管理
溶接・補強・防水・排水処理を一括管理 冬場の応急処置→春夏の本補修の連携体制
冬場の応急処置→春夏の本補修の連携体制 「溶接すればOK」ではなく、「通気性・勾配・施工歴」
「溶接すればOK」ではなく、「通気性・勾配・施工歴」まで踏まえた本質的な改善  外観回復(美観)+構造強化の両立
外観回復(美観)+構造強化の両立
6. 補修を進める際の段取りとチェックリスト
 スムーズな補修のための流れ
スムーズな補修のための流れ
- 調査依頼・現地確認(無料見積)
→ 問題のある鉄部の状態をプロが点検し、写真付きで報告
- 補修方法・材料・工期の提案
→ 小規模補修〜部分補強、構造改善までのパターン提案
- 施工スケジュール調整
→ 入居者やオーナー様の都合に配慮した段取りを組みます
- 補修施工(1〜5日程度)
→ 施工中も安全対策・音対策を徹底
- 完了報告・アフター確認
→ 写真・報告書による確認と、次回点検のアドバイスも
まとめ:鉄部劣化は防げる、早く対応すれば費用も安心
鉄部の腐食や劣化は、「目に見えたらもう末期」
だからこそ、
- サビが出始めた段階でプロに相談
- 冬前に点検・夏前に補修
- 再発を防ぐ構造改善まで一体対応
という方針で進めることが、入居者の安全・物件価値の維持・

 011-777-4771
011-777-4771 011-777-4771
011-777-4771
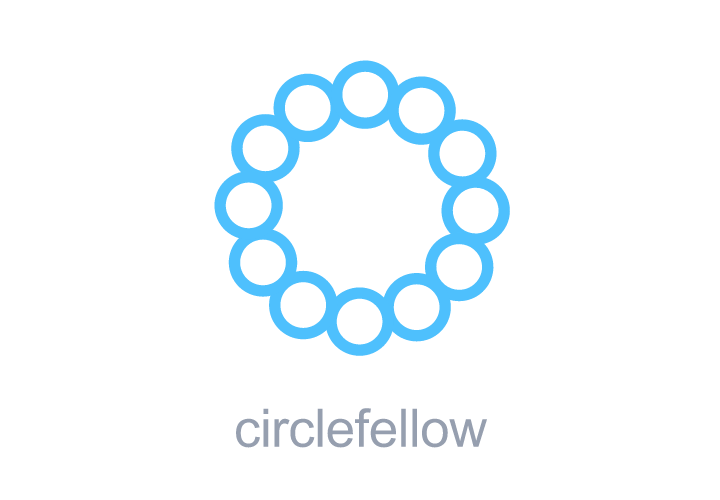
 目視+打診+裏側確認が基本
目視+打診+裏側確認が基本 補修方法:
補修方法: 北海道ならではの注意点:
北海道ならではの注意点: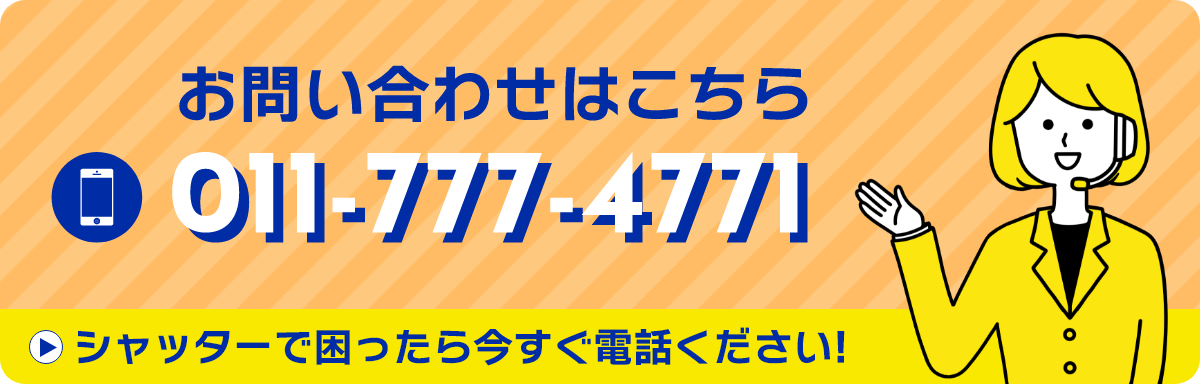
 改善策例:
改善策例: 鉄部の腐食進行度を診断し、
鉄部の腐食進行度を診断し、 スムーズな補修のための流れ
スムーズな補修のための流れ